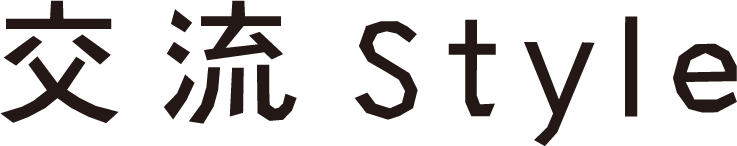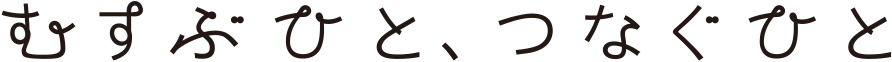
中部地域の注目パーソンにインタビュー!
手しごとと向き合い始めた原点とは
クラフト作家
上原 かなえ
(1/4)
February 17. 2025(Mon.)
長野県北佐久郡御代田町を拠点に、自身でライ麦を育て、その藁からつくるフィンランドの伝統装飾「ヒンメリ」で注目を集めているクラフト作家・上原かなえさん。地元でワークショップの開催や福祉施設「やまゆり共同作業所」と連携してライ麦ストロー制作など、精力的に活動の幅を広げている。
第1回目の今回は、そんな上原さんの「手しごと」との出会いについて語ってもらった。


両親、そして祖母の姿から
手しごとの楽しさを学ぶ
上原かなえさんは、小学校から高校を卒業するまで、父の故郷である鹿児島で過ごした。
両親はともに手を動かすことが大好き。父はサラリーマンだったが、趣味で絵を描いており、母は、自宅に近所の方たちを集めてキルトのワークショップを開いていた。
なかでも上原さんが最も影響を受けたのは、祖母だった。上原さんの父を女手一つで育て上げた祖母は、80歳を超えてもなお、自宅で洋裁の仕事を続けていた。
「祖母はとにかく手先が器用で、自宅にお客さまを招いて服を手づくりしていました。私が高校生になって将来の進路を考えていた頃も、まだ常連の方が来ていましたね」
自宅の2階で洋裁をする祖母の姿は、今の上原さんの活動にも重なる部分がある。
祖母の影響で自然と洋裁をするようになった上原さんは、パターンの引き方を教わり、自分で洋服をつくるうちに、デザインの仕事に興味を持つようになっていった。


ありました」と話す上原さん。
グラフィックデザインから
日本の伝統工芸の世界へ
故郷の鹿児島を離れ、東京のデザイン学校に進学した上原さん。当時はパソコンが普及し始めた頃で、グラフィックデザインや映像制作を学ぶのがトレンドだった。上原さんも当然のように最先端の技術を学び、卒業後、アパレルメーカーでグラフィックデザインの仕事に就いた。
ちょうどその頃、運命の人と巡り会った。上原さんの憧れの存在であった、グラフィックデザイナーのセキユリヲさんである。
「最初のうちはサインをお願いしたいと思うくらいの雲の上の存在でした」
その後、セキさんが生み出すグラフィックを洋服や雑貨にすることに。そして、その雑貨ブランド「salvia(以下 サルビア)」に、アパレルメーカーでデザインを手掛けてきた上原さんも立ち上げメンバーとして参加することになった。
サルビアの活動のなかで、セキさんと一緒に日本の伝統的な手しごとを見つけ、その職人さんの工房を巡った。今でこそ見直されつつある日本の伝統工芸だが、当時は衰退の一途をたどっていた。そこにスポットライトを当てて自分たちのデザインを融合させ、新たなプロダクトを生み出していく。こうした活動に夢中になって取り組んだ。
一念発起し
デンマーク留学を決意
サルビアの活動で、上原さんが特に力を入れていたのが、手しごとの楽しさを伝えることだった。なかでも、小さい頃から身近だった手しごとやキルト教室の様子を見てきた経験が役立ったのが、廃校となった小中学校の校舎を利用した「IDD世田谷ものづくり学校」でのワークショップである。上原さんは当時、ペーパークラフトの作家活動をはじめており、ペーパークラフトを通して「手づくりのすすめ」を提案する活動をスタートさせていた。
「手しごとの良さって、体験してみるとよく分かるんです」と上原さん。ワークショップを通じて、自分の手を動かしてもらう。そこに自分ならではの役目を見出した彼女は、グラフィックデザインから手しごとの世界へと徐々にフィールドを移していった。
「幼い頃の環境が蘇り、自分の原点に戻っていくような感覚でしたね」
そして2010年頃、再び転機が訪れる。
ともに活動してきたセキユリヲさんが、スウェーデンにある手芸を学ぶ学校へ軽やかに行ってしまった。そして帰国後、「あなたも行った方がいいよ」と勧められたのである。
はじめのうちは「もちろん行きたいけれど、そんなの夢の話だよね」と躊躇していたが、「ここまでやってきたことを振り返り、次のステップに踏み出すための良い糧になるのではないか」と一念発起。いろいろと調べた中で、年齢制限も入学試験もなく外国人の受け入れ枠もあり、手しごとに特化したデンマークの手工芸学校に留学することを決めたのだった。




夢のような世界で
手しごとと向き合う日々
上原さんがデンマークで学んだのは、「フォルケホイスコーレ」と呼ばれる国民学校だ。年齢制限がなく、一定数の外国人も受け入れており、さまざまな世代の学生が宿舎で共同生活を送る。数ある学校のなかで、上原さんは手しごとを専門的に学べる学校を選んだ。
そこには夢のような世界が広がっていた。
せわしない東京とは時間の流れがまったく違い、窓の外にはのどかな牧草地が広がっている。もちろん高層ビルなどは一切ない。自然と同じ速度で物事が動いていて、手しごととじっくり向き合うには絶好の場所だった。
みんなで暮らし、ともに学び合う。先生と生徒という上下関係も存在せず、上原さんもペーパークラフトの講師役を務めた。
作品の優劣を競うこともなく、純粋にものづくりを楽しむ人たちに囲まれながら、手しごとの魅力に改めて触れた上原さん。そしてこの留学をきっかけに、のちに活動の柱となる「ヒンメリ」と出会うことになった。
プロフィール
- クラフト作家
- 上原かなえ(うえはら かなえ)
- 北欧に古くから伝わる手しごとを研究し、ペーパークラフトやヒンメリなど身近な素材を用いた作品づくりを続けるクラフト作家。長野県北佐久郡御代田町在住。ヒンメリの材料となるライ麦を種から栽培するほか、地域の福祉施設と連携してライ麦の茎をドリンク用ストローに加工する「MIYOTAライ麦ストロープロジェクト」も主宰。決して無理をしない、地域に根差したサステナブルな活動が、多くの人たちの共感を呼んでいる。
- https://www.instagram.com/miyota_ryestraw/