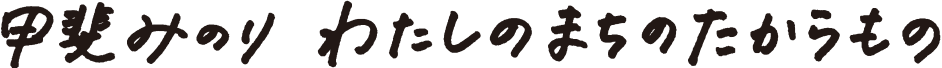
中部地域のさまざまなまちを文筆家・甲斐みのりさんが訪ねます
もっと居心地良い温泉街へ
道を拓く新しい風
渋温泉(長野県山ノ内町)
January 07. 2026(Wed.)
ー前回までの記事はこちら
1/4
海外からも脚光を浴びる 山間の温泉街 渋温泉(長野県山ノ内町)
開湯1350年の歴史がある長野県の渋温泉。江戸時代は草津温泉と善光寺を結ぶ草津街道の宿場として多くの人に利用され、愛されてきました。同時に、地元の人たちは九つの外湯を大切に育てあげ、湯宿に宿泊する客人をもてなしています。そんな風情ある温泉街に近年、新たな風が吹き込まれているというので、訪ねてみました。
今回は、旅館「かどや」を運営する株式会社ヤドロクの石坂大輔さんのほか、渋温泉でいろいろなことに挑戦するおふたりの活動をご紹介します。


温泉街に生まれる
新たな「場」
2015年から、小石屋旅館の経営を皮切りに、渋温泉で旅館業を営む石坂さん。まず考えたのは「お客さまにストレスなく滞在してもらうこと」だそうです。
前記事でもご紹介した「洋食を出す」こともその一環です。渋温泉は欧米からの旅行客が多いことから、とくに朝食は食べ慣れたバゲットのサンドイッチやエスプレッソが喜ばれるそうです。
もちろん、現在運営している「かどや」でも食事の方針は踏襲。さらには、気軽に宿泊できるようにと、無人でチェックイン・チェックアウトができる仕組みをつくりました。
また、彼らは夜間帯の消費を取り込むナイトエコノミーを重視する傾向があり、夜出歩きたいとか、ちょっと1杯飲みに行きたいといった需要があるそう。そこで、1、2杯軽く飲めるスタンディングバーをつくり、大変喜ばれています。これまで、近隣の温泉に入ったあと、お風呂上がりにちょっと飲みたいとの声は多かったのですが、渋温泉にはそういった店や施設がありませんでした。お客さまの7割はインバウンドなので基本的に英語で対応できるスタッフがカウンターに立っています。
かどや
https://yadoroku.jp/kadoya/
https://www.instagram.com/shibuonsen_kadoya/


日本に移住してかどやで働くウムトさんとの
会話を楽しみながら湯上がりに一杯。




老舗旅館も
さまざまにチャレンジ
石坂さんと思いをともにするのが、かどやの隣にある創業1600年の老舗旅館「古久屋(こくや)」の17代目・小根澤宏介さん。一度、実家の古久屋を出て銀行で働いた後、2018年に28歳で家業を継ぎました。
「当初はプレッシャーが大きかったけれど、今はお客さまやスタッフ、地域の方に支えられながら楽しくやっています」と小根澤さん。
「父も比較的新しいことに挑戦する方で、渋温泉の中でも早期に公式のWebサイトや予約システムを整えたり、客室に露天風呂をつくるなど豊富なお湯を活かしたりと、お客さまの誘致を進めていました。30年ほど前はまだ団体客が多かったのですが、Webサイトを開設して個人のお客さまの集客をはかりました。入口で温泉卵の無人販売を始めたのも先代の頃から。温泉卵は海外の方も珍しいらしく、写真を撮って楽しまれています」。
そうして自身の代になったとき、まずは、従業員の待遇の改善に取り組んだそう。「まずはスタッフに喜んでもらい、笑顔でお客さまをお迎えしてほしい。そう心がけました」。かどやを運営する石坂さんの考えとも重なります。こうして、もてなす側の環境も少しずつ変わってきたのでしょう。



目を引かれるのが、古久屋の前にあるトゥクトゥクです。最寄駅である湯田中駅から、渋温泉の中心部にある古久屋まで、トゥクトゥクでの送迎を取り入れました。
「父が東南アジアに旅行するのが好きで、移動の際に3人乗りくらいのトゥクトゥクを足代わりに使ってたんです。私も何度か一緒に行ったことがあり、これを渋温泉に持ってくることはできないかと父と考え、業者を探し、まち並みの雰囲気に合うようにデザインしてもらいました。乗る方も楽しんでもらえますし、見かけた人も笑顔になってくれます。小さなお子さんも、見かけると声をかけてくれて、ちょっとずつ認知されてるかなと思います」。
さらに、古久屋とかどや共同で、冬に芸者ショーを開催しています。古久屋のロビーでショーを見て、終わった後にかどやのバーに移っていただく。渋温泉には昔、最大200人もの芸者がいたそうですが、現在は一人だけ。その芸者さんに芸を披露していただける貴重なイベントです。
実は、石坂さんに、古久屋の隣のかどやを受け継ぎませんか?と声をかけたのも小根澤さん。旅館ぐるみの付き合いに限らず、旅館組合の役員を一緒におこなうなど、助け合っているといいます。
古久屋
https://www.ichizaemon.com/
https://www.instagram.com/shibu_onsen_kokuya/


デザインしたのは地元で知り合いの八百屋さん。


これまでなかった
カフェスペースが大人気
チェックイン前やチェックイン後に旅行者がくつろげる場所として人気を博しているのが「若葉屋」です。昭和から続く土産物と饅頭の店でしたが、現店主・関 亮太さんの叔父が温泉街で需要があるだろうとジェラートマシンを導入。しかし直後に叔父が亡くなり、亮太さんはその意思を継ぐべく、一からジェラートの勉強を始めたそうです。10年ほど前から販売を開始し、2024年にはカフェスペースを新設しました。
ジェラートは、いちご、杏、桃、柿、ぶどう、りんご、洋梨、牛乳など、できるだけ地元の素材を使用。チーズケーキなどの焼き菓子は、妻の祥予さんが担当しています。
亮太さんは、地元を離れていた時期もあったそう。
「趣あるまち並みがあるのに、自分たちの世代が通える店がなく、新しいものが生まれてなかったんです。それをなんとかしないと、温泉街自体が元気がなくなる。では、うちの店で何ができるかと考え、旅行客がひと息つける場所があれば喜んでもらえるし、湯上がりにコーヒーを飲んでくつろいでもらえる。そんなコンセプトで店づくりをしました。チェックイン前にコーヒーを飲んで、夜はジェラートを食べに来て、風呂上がりにビールも飲める。温泉街の宿木的な存在になれたらと思っています」。
亮太さんは若葉屋の運営以外にも、映像の仕事もされています。「地元の人が地元のことをプロモーションすることが、結果的に自分の店にも返ってくると思ってるので。これから映像制作を通して、店や温泉街を盛り上げることにも力を入れていきたい」ともおっしゃっていました。
若葉屋
https://www.instagram.com/wakabaya_shouten/




地元産食材を使い、季節によってフレーバーが変わる。




印象的だったのは、亮太さんが自身の店を「宿木のように」と表していたこと。確かに私も一つの旅の中で、次々と赴く先の数をこなすことに必死になっているところがありました。渋温泉で過ごす外国人旅行者は「寛ぎの達人」のように、ゆったりのんびりとしています。その姿を見て、大切な旅のあり方を思い出しました。そのためにも宿木となるお店は必要です。実際、若葉屋やかどやのスタンディングバー、古久屋の温泉卵は大人気で、みな思い思いに楽しむ姿が忘れられません。





